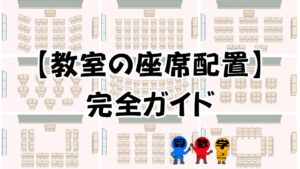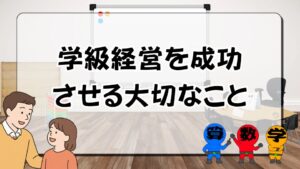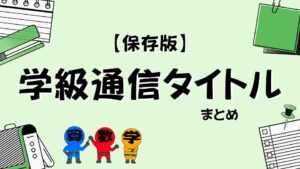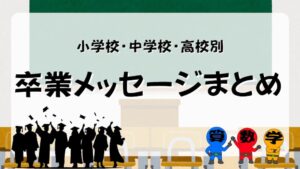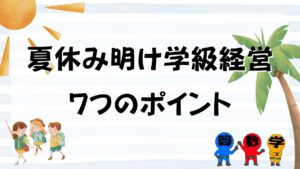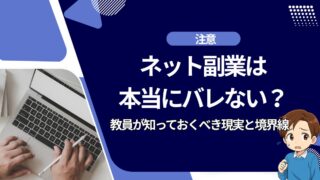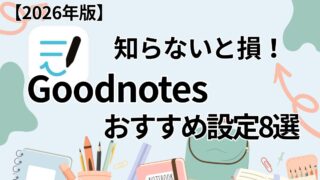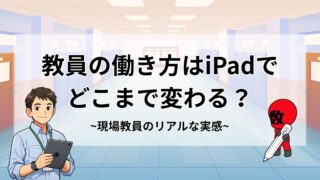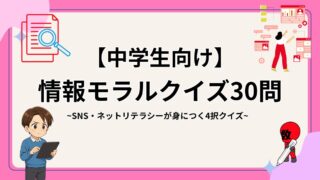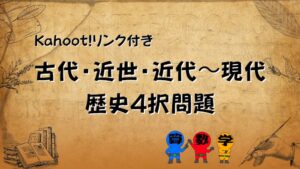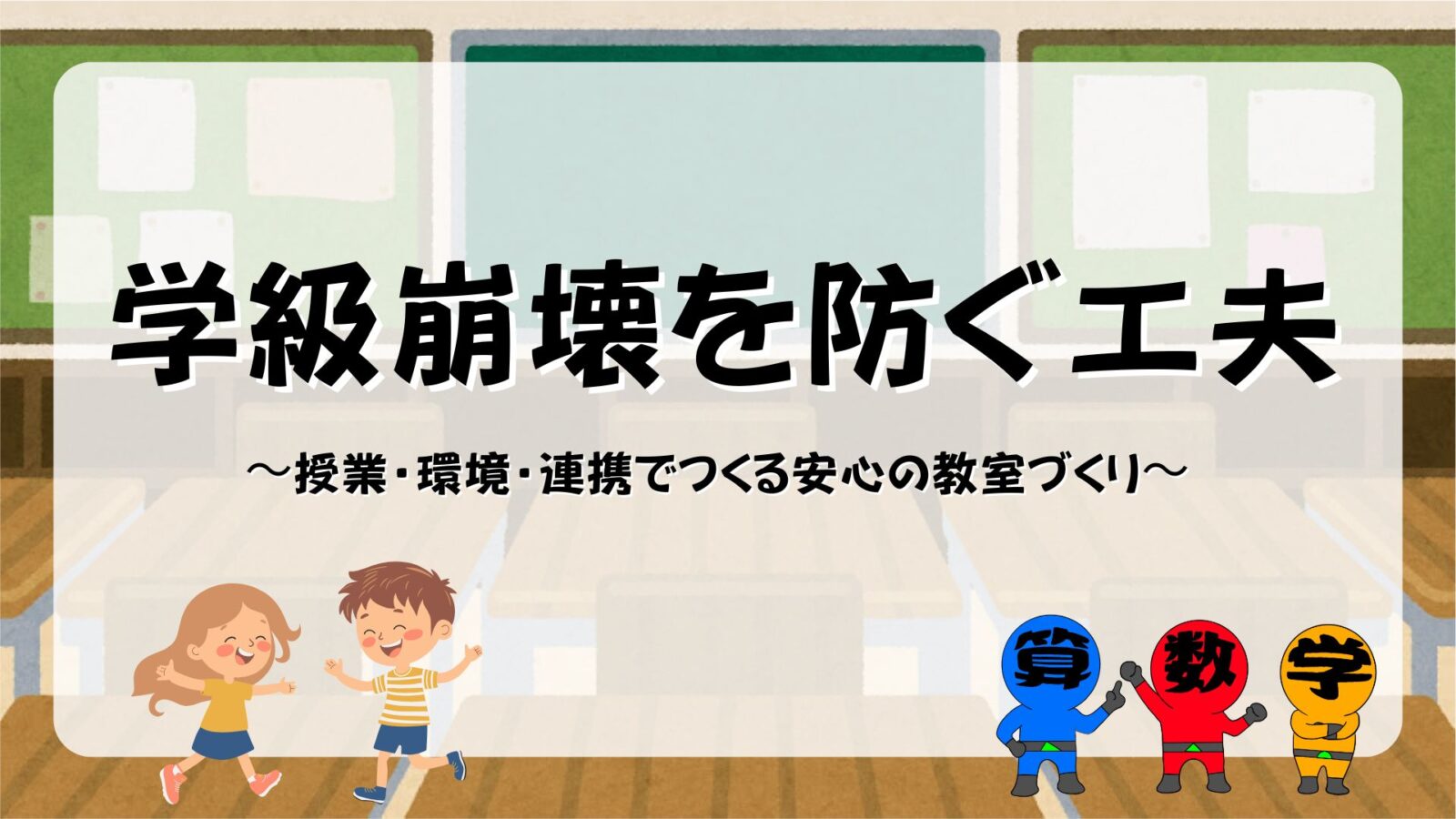
「学級崩壊」という言葉を耳にすると、「自分のクラスでは大丈夫」と思いたくなるのが正直なところです。けれども、実際にはどんな先生にも起こり得ることです。
私自身、これまでにクラスがうまくいかず、苦しい思いをした経験があります。
そんなときに一番大切なのは、一人で抱え込まないこと。そして、子どもたちの姿を通して「自分の指導をどう見直せばいいのか」を謙虚に考えていく姿勢です。
子どもたちの行動は、決して「先生への挑戦」ではなく、「もっと良い方法を探してほしい」というサインでもあると考えましょう。
この記事では、私自身の体験や周りの先生方から学んだ知恵を交えながら、学級崩壊を未然に防ぐための工夫を紹介します。
もし今、クラスづくりに悩んでいる先生がいたら、少しでも肩の荷を下ろして、「自分もできる」と思えるきっかけになれば嬉しいです。

私が意識している8つの工夫をご紹介します!
【2025年】教員の便利道具、おすすめアイテム70選を紹介!
【教室の座席配置】完全ガイド|9つの型とメリット・デメリットを紹介
学級経営を成功させる大切なこと|信頼関係・ルール・授業+実践のヒント
【保存版】学級通信タイトル500選|定番からユニークまでジャンル別まとめ
- 1. 学級崩壊とは?なぜ起きるのか
- 1.1. 学級崩壊の定義と現状
- 1.2. どうして起きる?背景と原因
- 1.2.1. 担任が“一人で抱え込む”構造
- 1.2.2. 教職員同士の連携体制の乏しさ
- 1.2.3. 児童個々の発達ニーズの多様化への対応不足
- 2. 教師の姿勢と心構え
- 3. 学級崩壊を防ぐ8つの工夫(実践編)
- 3.1. 工夫1:「楽しい授業」が最大の予防策
- 3.2. 工夫2:ルールを明確にし、徹底する
- 3.3. 工夫3:子どもの様子を細かく把握
- 3.4. 工夫4:個別対応とスモールステップ
- 3.5. 工夫5:約束・笑顔・ほめる・信じる
- 3.6. 工夫6:役割と目標を与える
- 3.7. 工夫7:チームで支える体制づくり
- 3.8. 工夫8:「怒るライン」を明確にする
- 4. まとめ
学級崩壊とは?なぜ起きるのか
学級崩壊の定義と現状
神奈川県教育委員会によると、「学級崩壊」とは授業中に児童が立ち歩いたり私語が多かったりして、教員の指示に従わない状態が おおむね1か月以上続き、正常な学習活動ができない学級 を指します。
さらに平成21年度に県内公立小学校全体の約 1.1%(162学級)だったこの状況が、平成28年度には全体の約 1.4%(199学級)に増加。1学年から6学年まで、どの学年でも起こり得る状況だという点も重要です神奈川県公式サイト。
このような学級が生まれると、子どもたちは学校やルール、さらには大人そのものに対する不信感を抱くようになる可能性があります。
どうして起きる?背景と原因
担任が“一人で抱え込む”構造
小学校の担任は多くの教科を一手に引き受けるため、学級の様子が外部から見えにくかったり、気づいてもサポートを求めづらい状況になりがちです。
「自分のクラスだから……」と抱え込み、一人で解決しようとしてしまうことが少なくありません神奈川県公式サイト。
教職員同士の連携体制の乏しさ
また、学年会や調整会議が形骸化していたり、経験の少ない教職員が多く、中核的な教員が担い手として孤立しているケースもあります。その結果、チームとして支え合う体制が整わず、結果として学級運営がうまくいかなくなる構造的な問題も見逃せません神奈川県公式サイト+1。
児童個々の発達ニーズの多様化への対応不足
近年は、発達のあり方が一様ではない児童が増えており、従来の指導スタイルでは対応しきれないケースが増えている点も背景にあります神奈川県公式サイト東洋経済オンライン。
たとえば、愛着課題や発達障害のある子どもへの支援的配慮の必要性は日増しに高まっていますみんなの教育技術家庭教師のあすなろ。
教師の姿勢と心構え
学級が荒れ始めると、つい「子どもたちの問題行動」にばかり目が向いてしまいます。
しかし、荒れは決して「子どもだけの問題」ではなく、子どもたちからのサインでもあります。私自身、クラスが落ち着かず私語や立ち歩きが増えたとき、「なぜこんなことが起きるのか」と悩み続けた経験があります。
そのとき大切だと気づいたのは、「自分の指導を謙虚に見直す」姿勢です。子どもたちには「失敗しても直せばいい」と伝えているのに、教師である自分が修正できないままでは説得力がありません。
むしろ「先生は自分のことを棚に上げている」と見抜かれ、信頼を失ってしまいます。子どもたちは、大人の背中を敏感に見ています。教師自身が「間違えたら直す」範を示すことが、学級の空気を落ち着かせる第一歩です。
また、教師の心構えは大きく二つに分かれると感じます。
- 子どものことを本気で考える教師
- 楽をしたいと考える教師
正直に言えば、私自身も「注意するのが面倒だな」と思ったことが何度もあります。けれども、そのたびに「本気で子どもを考える教師でいなきゃいけない」と自分に言い聞かせました。
本気で子ども向き合う教師は、周囲に流されず、子どもの行動の背景にある思いや困難にまで目を向けるはず。一方で、楽を選んでしまえば、問題はどんどん積み重なり、結果的に教師自身を苦しめることになるのです。
学級の荒れは「教師一人で抱えるもの」ではありません。学年や学校全体で支え合うことも不可欠ですが、同時に「教師自身の姿勢」が子どもたちに与える影響は絶大です。
自分が範を示し、本気で子どもの成長に向き合う――この覚悟が、学級崩壊を未然に防ぐ最大の土台になります。
荒れないクラスは環境から|1〜3年目の先生に伝えたい教室づくりの工夫
【小中高校別】卒業メッセージ210選|四字熟語・名言・英語・面白いフレーズも紹介
夏休み明けの学級経営7つのポイント|実体験からわかるクラスが荒れない工夫
学級崩壊を防ぐ8つの工夫(実践編)
工夫1:「楽しい授業」が最大の予防策
私の経験から言っても、授業がつまらないと子どもは必ず荒れます。私語、ちょっかい、立ち歩き…。どれも「授業に魅力がないサイン」なのです。
逆に「授業が楽しいから邪魔されたくない」という雰囲気を作ることができれば、自然と規律は整っていきます。
学級経営においてよく言われる「黄金の三日間」も、実は授業の質に直結しています。冒頭の数時間で「この授業は面白い」「この先生ならついていきたい」と子どもに思わせられるかが、その後の学級の雰囲気を決定づけるのです。
準備を怠らず、子どもを夢中にさせる授業づくりこそ最大の予防策だと実感しています。
工夫2:ルールを明確にし、徹底する
子どもたちは「曖昧さ」に不安を感じやすいものです。特に自閉症傾向のある子にとっては、「やっていいこと・いけないこと」がはっきりしていないと混乱し、落ち着かなくなります。
例えば私は、チャイム着席のルールや掃除のやり方を徹底させています。また、やるべきことを一目でわかるように TODOリスト のようなものを掲示しておくのも効果的です。
ルールを全員が共有し、徹底することで、子どもたちの安心感は高まり、教室の落ち着きにもつながります。
工夫3:子どもの様子を細かく把握
学級崩壊を未然に防ぐためには、小さなサインを見逃さないことが大切です。
私は下駄箱の靴の揃え方、ロッカーの整頓具合、提出物の状態、名札の扱い方などを日常的に観察しています。こうした何気ない部分に、子どもの心の状態は表れるのです。
また、放課後に子どもと散歩する時間を意識的に作ります。こうした時間にこそ、授業中には見えない子どもの本音を聞けることがあり、信頼関係づくりにもつながります。
工夫4:個別対応とスモールステップ
全体の指導だけでなく、個別の対応も欠かせません。私語が多い子には席を前列に変える、あるいは後方に下げて自分のペースで学べる環境をつくるなど、子どもの特性に応じた調整が必要です。
また、集中が続かない子には「まず10分だけ」「まず5問だけ」というスモールステップを意識させます。
できたことを積み重ねて達成感を味わうことで、徐々に落ち着きを取り戻し、自信を持って学習に向かえるようになります。
工夫5:約束・笑顔・ほめる・信じる
子どもたちから信頼を得るには、教師自身の姿勢が最も大きな影響を与えます。
- 約束は絶対に守ること。些細な約束でも軽んじない。
- 笑顔と声のトーンで明るい空気を作ること。
- ほめる言葉のバリエーションを増やすこと。
- 叱った後はすぐに笑顔で接すること。
私もかつて、叱った後につい表情が険しくなり、子どもとの距離が広がってしまったことがあります。しかし「握手=仲直り」を合図にしたところ、子どもたちは安心して学級に復帰できるようになりました。
工夫6:役割と目標を与える
「やることがないから荒れる」子どもは少なくありません。そんなときは、係活動や整頓キャンペーンなど、役割を持たせることが効果的です。
誰かに必要とされる経験が、子どもの居場所や自己有用感を育てます。
また、学級全体で取り組む目標を掲げるのも効果的です。例えば「毎朝のあいさつ習慣」「月1回のお楽しみ会」など、全員で達成感を味わえる活動は、クラスの団結を深め、荒れを防ぐ大きな力になります。
工夫7:チームで支える体制づくり
何より大切なのは、一人で抱え込まないことです。学級崩壊は担任の力量不足ではなく、子どもの多様な背景や学校環境が複雑に絡み合って起こるものです。
学年主任や管理職、スクールカウンセラー、通級指導担当などに早めに相談し、チームで支える体制をつくることが鉄則です。
保護者との情報共有も密にしておきましょう。専門家の視点を取り入れることで、教師一人では気づけなかった解決策が見えてくることも多いのです。
工夫8:「怒るライン」を明確にする
私が考える一番大切なことが 、先生が「怒るライン」を明確にすること です。
子どもは大人の表情や声色を敏感に読み取り、「今日は先生の機嫌がいいから許される」「昨日は怒られなかったのに、今日は怒られた」といった矛盾を感じると、ルールそのものを軽視してしまいます。
そこで必要なのは、「これだけは絶対に許さない」ラインを明確に言葉で示し、守り抜くことです。
- 「友達を傷つけることは絶対に許さない」
- 「授業を妨げる行動はその場で止める」
- 「先生や仲間を侮辱する言葉は一切認めない」
このように「教師の一貫した姿勢」を貫くことで、子どもは「どこまでが大丈夫で、どこからが越えてはいけないのか」を理解し、安心して学級生活を送れるようになります。
また、教師が感情的に怒鳴るのではなく、ルールを破ったら淡々と対応する姿勢を続けることも重要です。
感情や気分に左右されず一貫した態度を貫くことで、学級全体に「安心できる枠組み」が築かれていきます。
まとめ
学級崩壊は、決して特別な学校や特定の先生だけに起こる現象ではありません。どの学級でも、誰のクラスでも起こり得るものです。
だからこそ、「自分のクラスは大丈夫」と思い込まず、日常的に予防の工夫を積み重ねることが大切です。
今回紹介したように、
- 授業改善
- ルールの明確化
- 子どもの様子を細かく把握
- 個別対応とスモールステップ
- 約束・笑顔・ほめる・信じる
- 役割と目標を与える
- チームで支える体制づくり
- 「怒るライン」を明確にする
これらを継続して取り組むことで、学級崩壊を未然に防ぐだけでなく、もしクラスが荒れたとしても立て直す力につながります。
先生の仕事は楽ではありません。ときに心が折れそうになることもあります。それでも、子どもたちの未来に関わる責任を胸に、周囲と支え合いながら前に進むことが大切です。
学級は「子どもたちの学びの場」であると同時に、先生自身が学び続ける場でもあります。日々の実践と振り返りを通して、一人ひとりの子どもが安心して成長できる学級を築いていきましょう。
投稿者プロフィール

-
現役で数学を教えている中学校の先生です。中学の数学のプリントやICT関連の情報、ブログでは道徳や学級レクのネタも発信しています。
このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。
最新の投稿
 お知らせ2026年1月18日ネット副業は本当にバレない?教員が知っておくべき現実と境界線
お知らせ2026年1月18日ネット副業は本当にバレない?教員が知っておくべき現実と境界線 ブログ2026年1月17日【2026年版】知らないと損!Goodnotesのおすすめ設定8選|作業効率が一気に変わる使い方
ブログ2026年1月17日【2026年版】知らないと損!Goodnotesのおすすめ設定8選|作業効率が一気に変わる使い方 ブログ2026年1月11日教員の働き方はiPadでどこまで変わる?現場教員のリアルな実感
ブログ2026年1月11日教員の働き方はiPadでどこまで変わる?現場教員のリアルな実感 ブログ2026年1月7日【中学生向け】情報モラルクイズ30問|SNS・ネットリテラシーが身につく4択クイズ
ブログ2026年1月7日【中学生向け】情報モラルクイズ30問|SNS・ネットリテラシーが身につく4択クイズ