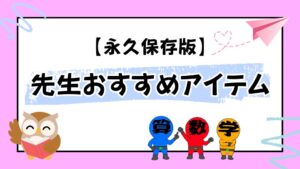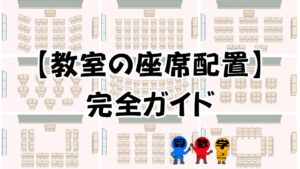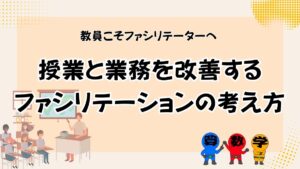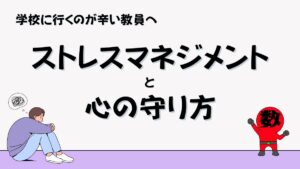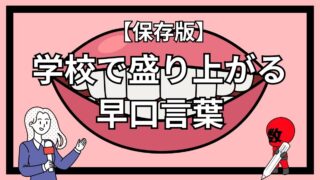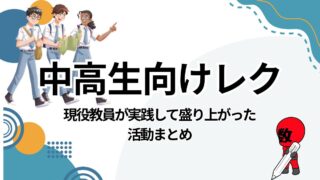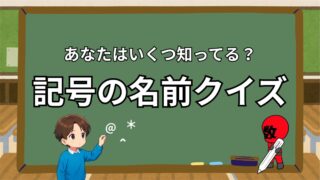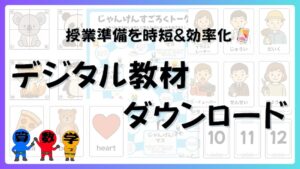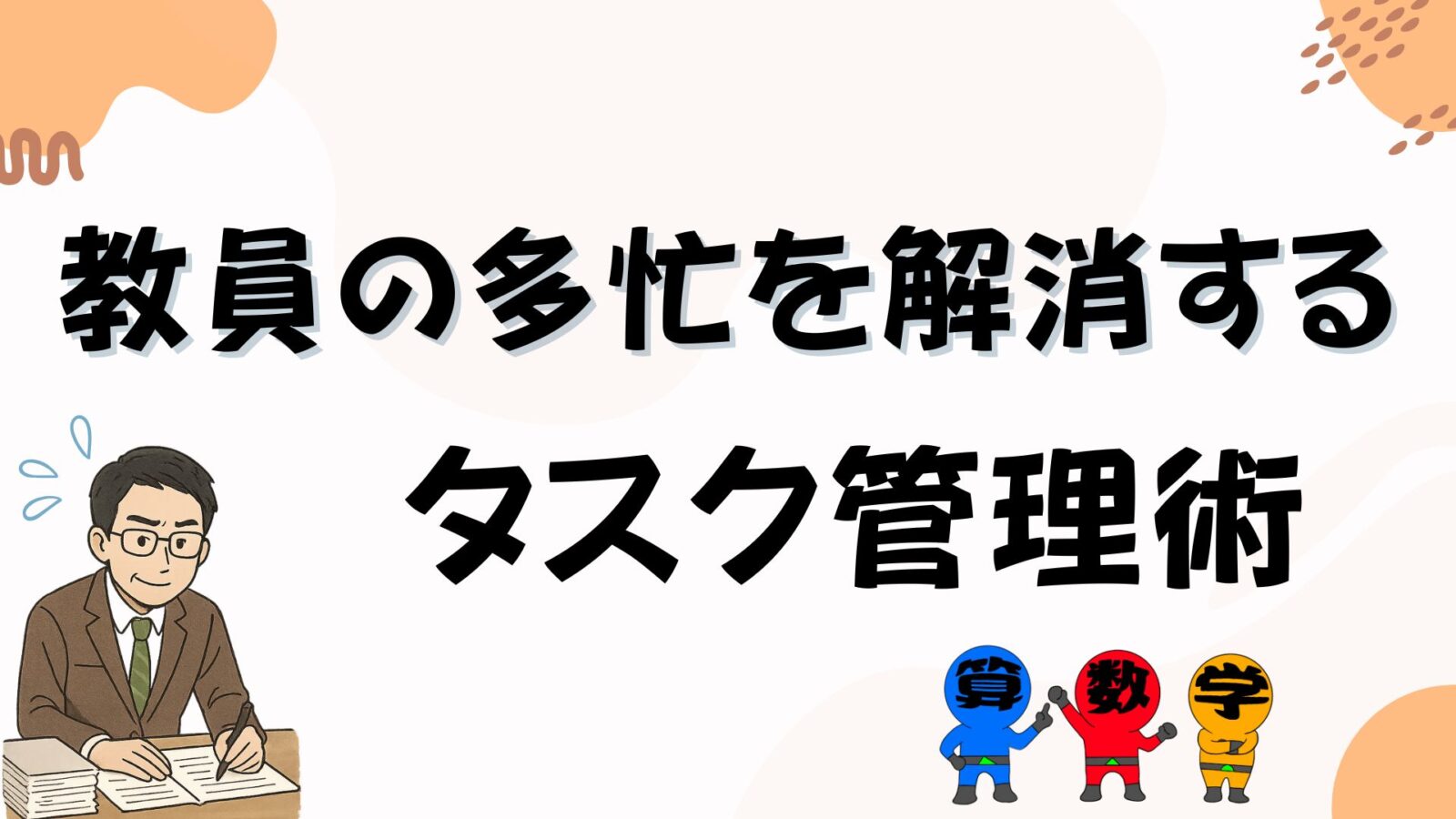
教員の仕事は本当に幅広く、授業はもちろん、保護者対応や生徒指導、事務処理など多岐にわたります。
1日4時間も5時間も残業すれば、確かに仕事は片づくかもしれません。しかし、私たちにはプライベートや家庭があり、時間は何よりも大切な資源です。毎日残業漬けでは、心も体も持ちません。
しかも、働き方改革がなかなか前に進まない中で、結局は「自分自身がどう効率化していくか」が問われています。私自身も教員生活の中で、タスク管理の方法を工夫してきました。
そのおかげで、以前よりも定時に近い時間で帰れるようになり、プライベートを充実させることができたと感じています。
この記事では、私が実際に取り入れてきたタスク管理の工夫を紹介します。同じように仕事を抱え込んでいる先生方にとって、少しでもヒントになれば幸いです。

この記事は、本気で業務を効率化したい先生向けですよ!
【2025年】教員の便利道具、おすすめアイテム70選を紹介!
【教室の座席配置】完全ガイド|9つの型とメリット・デメリットを紹介
荒れないクラスは環境から|1〜3年目の先生に伝えたい教室づくりの工夫
- 1. 教員が多忙に陥りやすい理由
- 2. 基本となるタスク管理の方法
- 3. 教員が実践しやすいタスク管理術
- 3.1. アナログ派におすすめの方法
- 3.1.1. 手帳
- 3.1.2. 付箋
- 3.1.3. ミニクリップボード
- 3.1.4. ノート
- 3.2. デジタル派におすすめの方法
- 3.2.1. Googleカレンダー
- 3.2.2. ToDoList・Google Tasks などのToDoアプリ
- 3.2.3. デジタルプランナー
- 4. GTD(Getting Things Done)の考え方を取り入れる
- 4.1. GTDの基本ステップ
- 4.2. 教員にとってのGTDの利点
- 4.3. 私の実践ポイント
- 5. さらに効率化する独自の工夫
- 5.1. 放課後5分ルール|翌日の準備を短時間で済ませる習慣
- 5.2. 3色ペン方式|優先度を色分けして一目で判断
- 5.3. 見えるデスク方式|机の配置で進捗を「見える化」する
- 6. 購入できるデジタルコンテンツの活用
- 7. タスク管理で得られる効果
- 7.1. 抜け漏れが減り、精神的な安心感が生まれる
- 7.2. 時間の見通しが立ち、定時退勤に近づける
- 7.3. 教育の質が上がり、生徒との時間を確保できる
- 8. まとめ|今日からできる小さな一歩
教員が多忙に陥りやすい理由
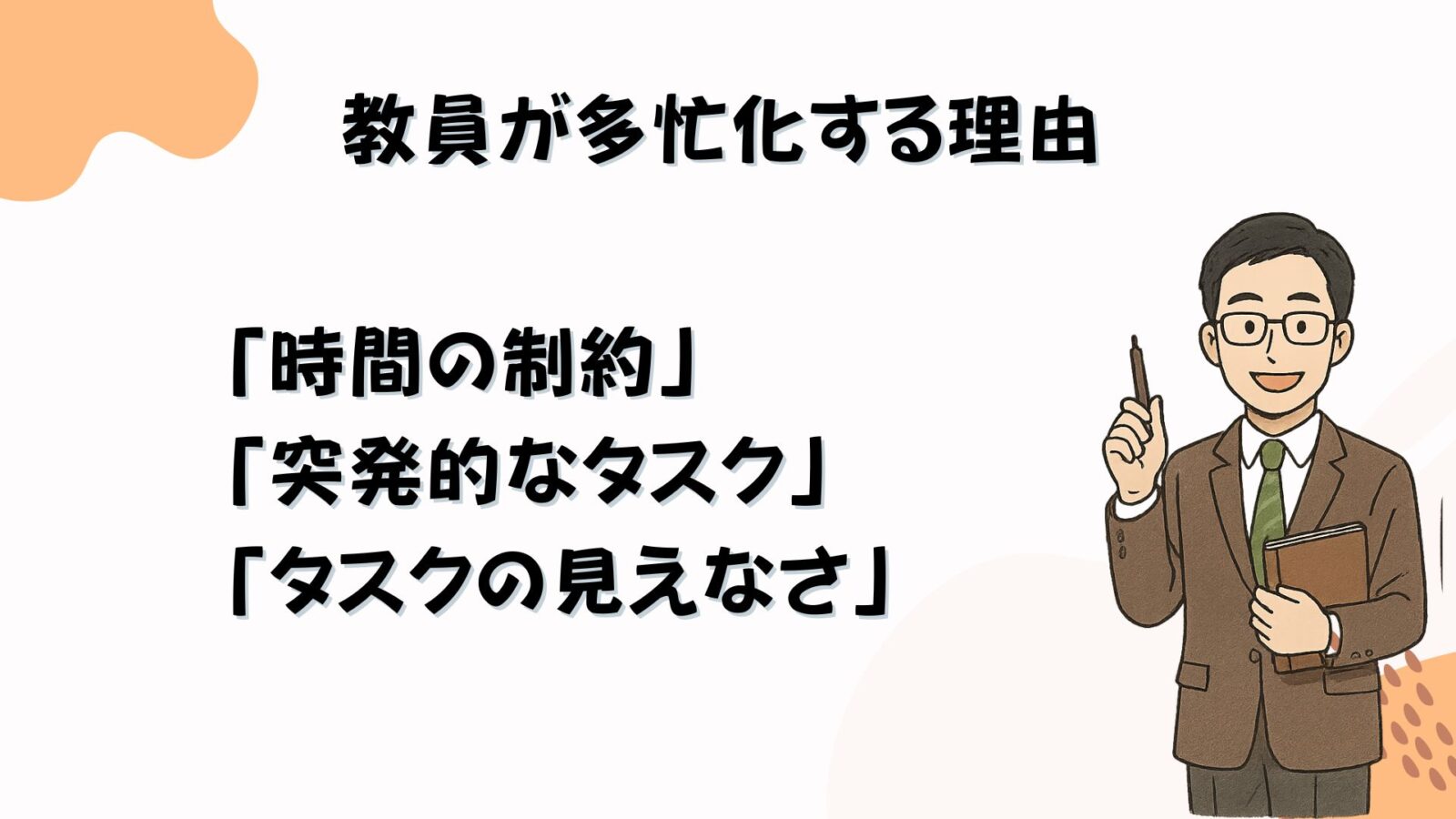
教員の仕事は一見すると授業が中心に思われがちですが、実際には授業準備以外の業務が膨大です。
会議、行事、事務処理、そして突発的な生徒対応。特に新年度の立ち上がりである4月、行事が立て込みやすい6月や10月、さらに定期テストと成績処理が集中する7月・12月・2月は、多忙のピークを迎えます。
私自身もこの時期は、まるでタスクの波に飲み込まれるような感覚を何度も味わってきました。(教員は1年中忙しいですが…)
加えて、教員は「自由裁量時間」が極端に少ない職業です。授業や会議といった決まった予定が大半を占めるため、いざ自分の仕事を進めようと思っても、割り込むように生徒のトラブルや保護者対応が入り込みます。
実際に、生徒同士のトラブルから保護者との緊急連絡に発展し、予定していた仕事が丸ごと後ろ倒しになったことは先生をやっていれば何度も経験しているはず…。
さらに問題を複雑にしているのが、「自分の仕事の全体像を把握できていない」という状況です。私自身、タスクを可視化していなかった頃は、優先順位が曖昧なまま夜を迎え、翌朝になって「これを今日中にやらなきゃ!」と慌てることが日常でした。
結局、頭の中が常にごちゃごちゃしている状態では、効率も悪く、心の余裕も奪われてしまいます。
こうした「時間の制約」「突発タスク」「タスクの見えなさ」の三重苦こそが、教員を多忙に陥れる最大の理由です。
この章のまとめ
- 生徒トラブルや保護者対応など、突発的なタスクが発生しやすい
- 授業時間が多く、自由に使える時間が限られている
- タスクの優先順位を整理できていないと「翌朝に焦る」状況になりやすい
- 結果として「常に追われる感覚」に陥り、改善が難しくなる
基本となるタスク管理の方法
教員のタスク管理の基本は「やるべきことを見える化し、優先順位をつける」ことに尽きます。これは文献でも繰り返し強調されている部分であり、私自身も15年間の教員生活で強く実感してきました。
まず欠かせないのがToDoリストの活用です。思いついたタスクは、デジタルでもアナログでも良いので必ず書き出しておくことが大切です。頭の中だけで覚えておこうとすると、抜け漏れや「何を優先すべきか」の判断疲れを招きます。
私は日頃、付箋や手帳にメモすることもあれば、スマホアプリを使うこともありますが、形にこだわらず「まずは外に出す」ことを徹底しています。
次に大切なのが優先順位付けです。特に保護者からの要望や問い合わせは最優先で取り組むようにしています。
経験上、保護者対応を後回しにすると、クレームや不信感に発展しかねません。逆にここを素早く処理しておくと、保護者との信頼関係がスムーズに築けるのです。
また、授業準備は前日の放課後と当日の朝に分割して行うのが私の習慣です。前日に8~9割を仕上げておき、翌朝に残り1~2割を見直す。直前に構成を振り返ることで「あ、ここは生徒に問いかけを入れた方がいいな」など気づくことが多く、授業がブラッシュアップされます。
この「朝の仕上げ時間」は、授業の質を高めるための大切なひと工夫だと感じています。
さらに、印刷物は空きコマか朝の時間に処理します。放課後はどうしても同僚と印刷機がバッティングしやすく、無駄に待たされる時間が発生します。
また、放課後は先生同士の会話で時間が取られてしまうことも多いため、私はなるべく「朝に片づける派」です。こうした小さな工夫の積み重ねが、結果的に仕事全体の効率化につながっていきます。
つまり、基本のタスク管理術は単なるToDoやカレンダーの記入にとどまらず、「どのタイミングで何をやるか」を意識して習慣化することが肝心です。
この章のまとめ
- ToDoリストはデジタル・アナログを問わず必ず作り、頭の中から外に出す
- 保護者対応は最優先で処理し、信頼関係を築く
- 授業準備は「前日9割+朝1割」でブラッシュアップ
- 印刷物は「朝や空きコマ」で処理し、放課後の混雑や会話に時間を奪われない
- タスク管理は「何をいつやるか」を習慣化することが肝心
教員が実践しやすいタスク管理術
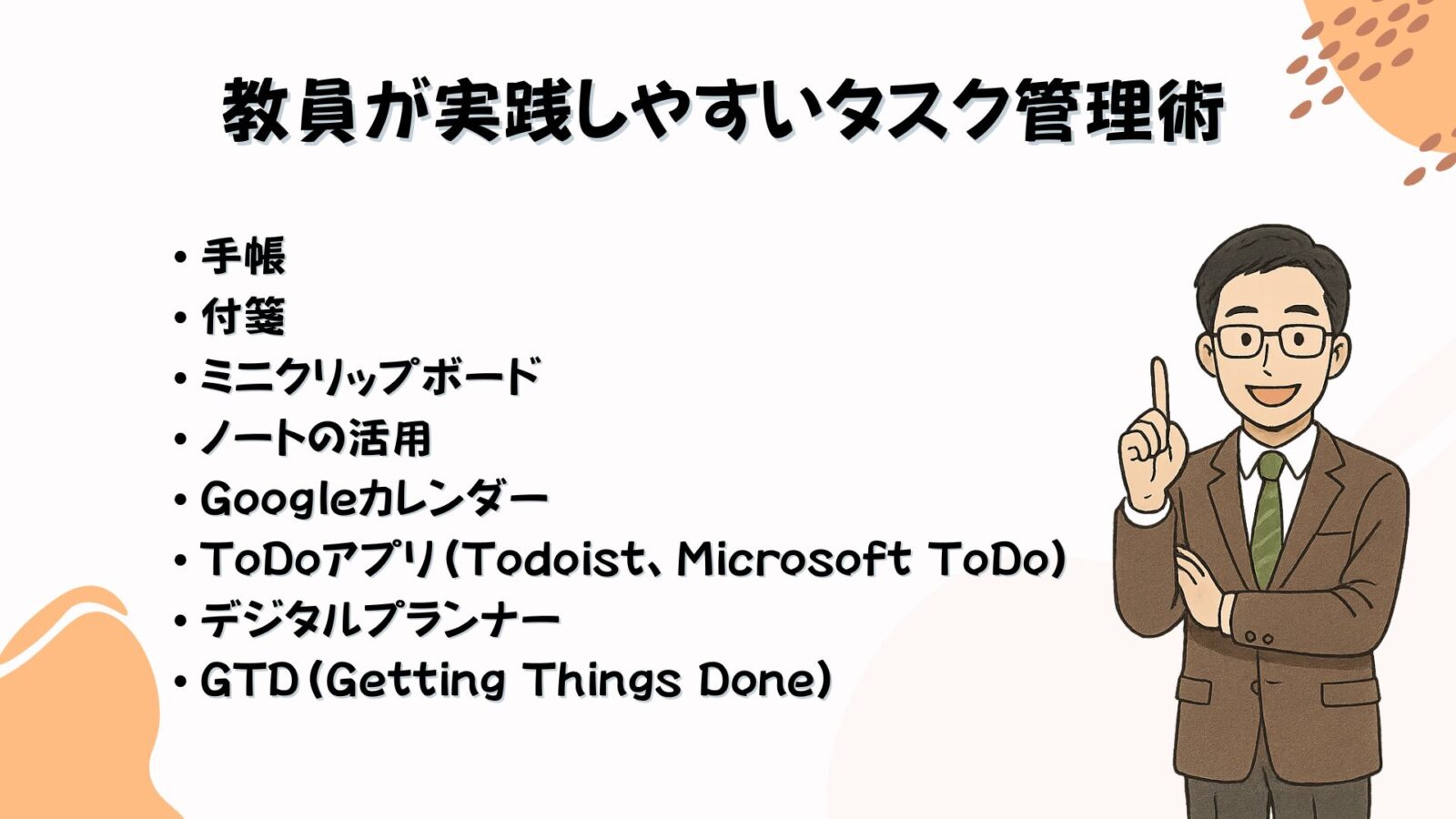
アナログ派におすすめの方法
手帳
教員向けの手帳(例:スクールプランニングノート)は、1年間のスケジュールを見通すために便利です。行事や校務分掌、授業計画、成績処理などを一覧化でき、全体の流れを把握しやすくなります。
さらに、授業準備や生徒指導の簡単な記録も残せるため、振り返りや翌年度の改善にも活用できます。
私自身も年間スケジュールはデジタルで管理しますが、「大きな見通し」を立てるにはやはり紙の手帳の良さがあります。特に紙面に書き込むと「時間の流れ」を直感的に把握できる感覚があります。
付箋
付箋は「今日中に必ず処理するタスク」を管理するのに効果的です。机や手帳に貼っておけば常に視界に入り、忘れにくくなります。また、退勤時に剥がして捨てることで「今日やるべきことをやり切った」という達成感も得られます。
私は基本的にはデジタルのものを使用していますが、突発的に入った「今日中やらなければいけない仕事」については、付箋に書いて机に貼っています。
ただし付箋は剥がれて紛失することもあるため、重要なものは必ずGoogleカレンダーやデジタルプランナーにも記録しておきます。
ミニクリップボード
1か月単位のタスクを管理するにはミニクリップボードが便利です。月初に手帳から「今月中にやること」を書き写し、新しいタスクが発生したら追記します。
期限が近いものは色ペンで目立たせておけば、優先順位も分かりやすくなります。机の上に置いておくことで、常に「直近のやるべきこと」を確認できるのが強みです。
ノート
ノートは、日々の授業準備や生徒対応の記録、打ち合わせのメモなど「記録を残す」用途に適しています。メモ帳だと失くした時のリスクが大きいですが、ノートにまとめれば情報が散逸しません。また、思考を整理するのにも向いているため、「考える作業」に使うと効果的です。
私は手帳や付箋に比べるとノートの使用頻度は少ないですが、「授業のアイディアをじっくり練るとき」にはノートに書きながら考えることがあります。
デジタル派におすすめの方法
Googleカレンダー
授業、会議、行事などのスケジュール管理に最適です。リマインダーを設定すれば、タスクの抜け漏れを防ぐことができます。さらに家族と予定を共有することも可能で、仕事と家庭の両立に役立ちます。
私は印刷物を作成する時間や放課後のちょっとした打ち合わせもGoogleカレンダーに入れておきます。重要なのは「タスクも時間でブロックしてしまう」こと。そうすることで「あれ、いつやるんだっけ?」という不安を防げます。
ToDoList・Google Tasks などのToDoアプリ
日々のタスクを細かく整理し、進捗状況を可視化できます。特にToDoListは「繰り返し設定」が便利で、ルーティンタスクを毎日自動で表示してくれるため、忘れるリスクを大幅に減らせます。
私は突発的に入った仕事はまず付箋に書きますが、それを後でToDoListに入力して整理します。大きなタスクも小さく分割して入れておくことで「次に何をするか」が明確になります。
デジタルプランナー
iPadなどで使える教員用のデジタルプランナーは、手書きの感覚とデジタルの便利さを兼ね備えています。
授業の記録や行事の予定を手書きで残しながら、検索やコピー・貼り付けといった機能も使えるため、アナログ派からの移行にもおすすめです。
私は特に「授業構成のメモ」や「来年度も使いたい記録」を残すときにデジタルプランナーを使います。
GTD(Getting Things Done)の考え方を取り入れる
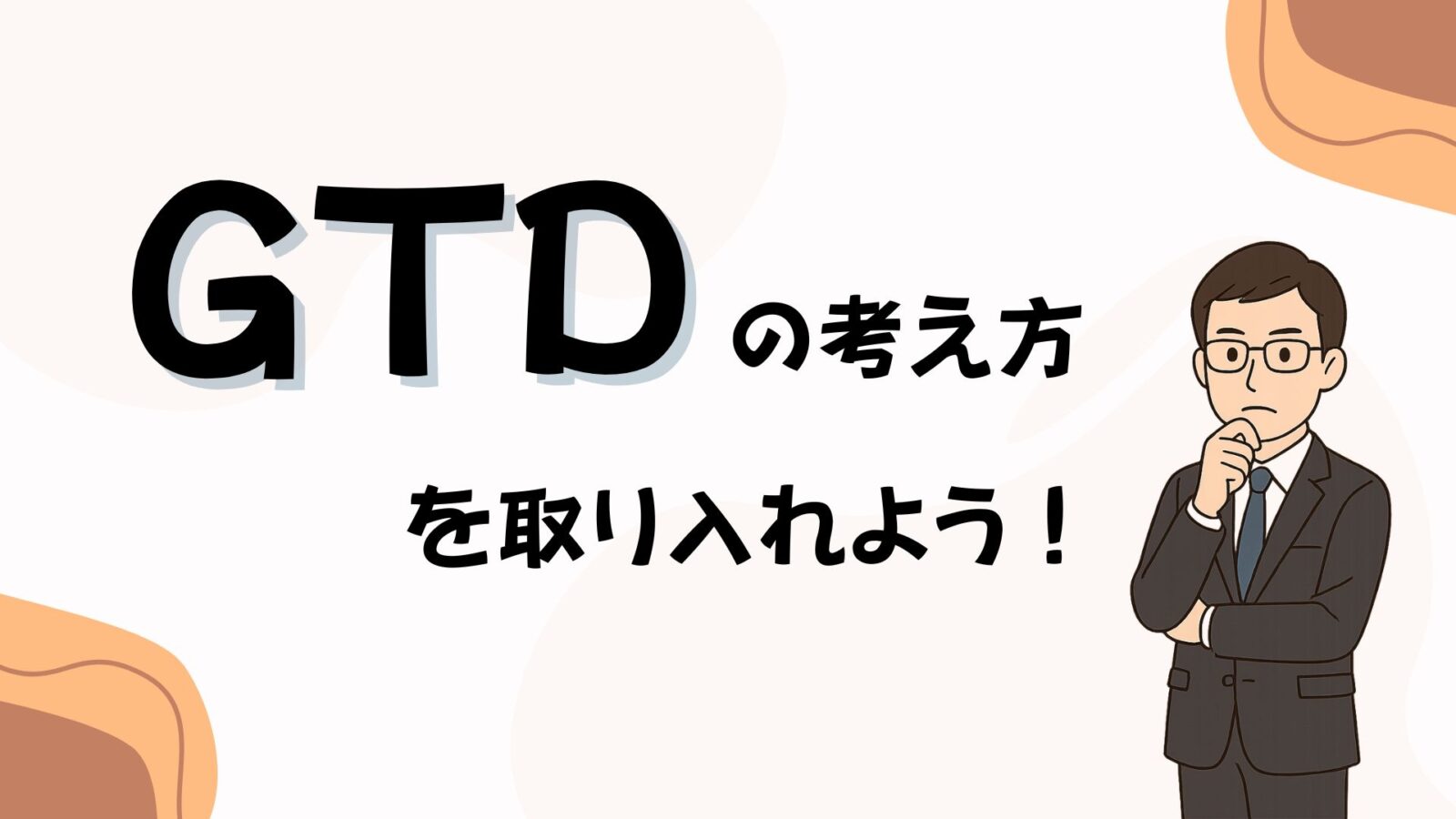
GTDとは、生産性向上コンサルタントのデビッド・アレン氏が提唱したタスク管理術で、頭の中の「やらなきゃ」をすべて外に出し、整理して行動に移すための方法です。
特徴は「とにかく一度すべてを書き出す」こと。頭の中に散らばるタスクを可視化し、状況に応じて処理できる形に整理していきます。
GTDの基本ステップ
- 把握:頭の中にあるすべてのタスクや気になることを外に書き出す
(授業準備・成績処理・保護者対応・プライベートの予定まで) - 見極める:行動が必要かどうかを判断し、不要なら削除。すぐ終わるものは即処理。
- 整理する:残ったものをプロジェクトやカテゴリに分ける。
例:授業、分掌業務、学年行事など。 - 更新する:定期的にリストを見直し、最新状態にする。
- 選択する:状況や優先度を見ながら、今やるべきことを選んで実行する。
教員にとってのGTDの利点
学校現場では、突発的な生徒指導や保護者対応で予定が崩れることが日常茶飯事です。その中でGTDは「タスクを一度外に出す」ことで、頭の中が整理され、精神的な余裕が生まれます。結果的に「次にやるべきこと」が見えやすくなり、無駄な判断疲れを防げます。
私の実践ポイント
タスクはその場で入力:会議や打ち合わせで仕事を振られたら、その場でアプリ(Todoistなど)に入力し、あとで整理。
ルーティンタスクもリスト化:日誌記入、出欠管理など、毎日必ず発生する仕事もタスクに入れておくと、抜け漏れ防止になる。
25分作業を基準に区切る:授業1コマ50分を基準に、タスクは「25分以内で終わる大きさ」に分解すると取り組みやすい。
さらに効率化する独自の工夫
放課後5分ルール|翌日の準備を短時間で済ませる習慣
私は、どんなに忙しくても「放課後5分」だけは翌日の準備にあてています。5分という短い時間でも、プリントを机に出しておく、必要な資料をまとめておく、授業の流れを頭の中で確認しておく──それだけで翌朝のスタートが驚くほど楽になります。
以前は翌朝に慌てて準備していましたが、このルールを徹底することで「授業直前の焦り」が減り、精神的にも余裕が生まれました。
3色ペン方式|優先度を色分けして一目で判断
タスクを処理するとき、私は3色のペンを使って優先度を色分けしています。
- 赤:今日中に必ずやること(授業準備・保護者対応など)
- 青:今週中にやること(成績処理や会議資料作成など)
- 緑:できればやりたいこと(教材研究・アイデアメモなど)
視覚的にパッと判断できるので、「次に何をすべきか」に迷う時間が減ります。色分けのおかげで、頭の中で「優先度の取捨選択」を繰り返す必要がなくなり、結果的に仕事が早く進むようになりました。
見えるデスク方式|机の配置で進捗を「見える化」する
机の上の使い方も工夫しています。
- 右側:これから処理するタスク(未処理のプリントや資料)
- 中央:今取り組んでいるもの
- 左側:処理済みのもの
こうしたシンプルな「動線管理」を徹底するだけで、デスクの上が自然と「進捗ボード」になります。以前は書類の山に埋もれて「どこまでやったっけ?」と探す時間が多かったのですが、この方式を取り入れてからは、仕事の進捗がひと目でわかるようになりました。ちょっとした工夫ですが、精神的にも整理された感覚が得られるのでおすすめです。
購入できるデジタルコンテンツの活用
最近は、教員向けの教材も オンラインで購入・ダウンロードしてすぐ使えるデジタル版 が増えてきました。印刷すればすぐに授業や学級経営に活用できるため、忙しい教員にとっては大きな時短につながります。
紙の教材と違って、デジタル教材には次のようなメリットがあります。
- 準備の手間を減らせる:ダウンロードしてすぐ印刷、あるいはタブレットで表示して使える。
- 繰り返し利用できる:一度購入すれば何度でも使い回せる。
- カスタマイズが可能:必要に応じて一部だけ印刷、カラー・白黒の使い分けも自由。
- 保管が楽:場所を取らず、PCやクラウドに保存できる。
私自身もこうしたデジタル教材を作成・販売しています。授業の導入や学級経営のアイデアとして活用いただけるよう工夫しました。
👉 興味のある方は、ぜひこちらの クリエイターページ をご覧ください。
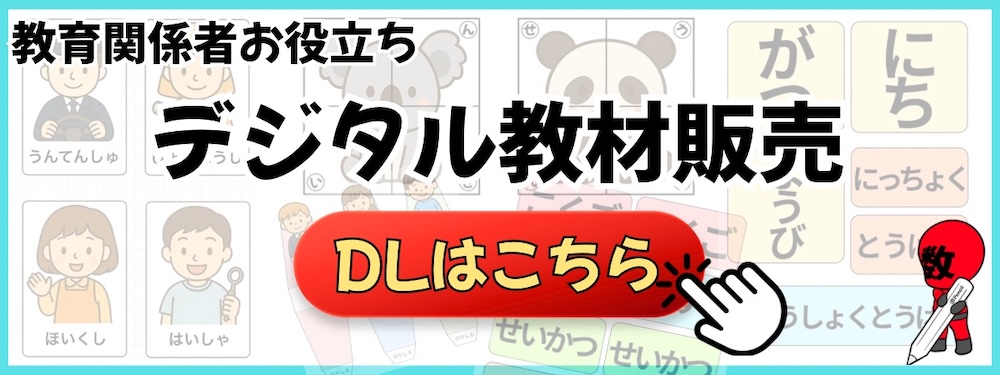
タスク管理で得られる効果
抜け漏れが減り、精神的な安心感が生まれる
教員の仕事は「やることリスト」を頭の中だけで抱え込むと、常に「あれもやらなきゃ」「忘れていないかな」という不安がつきまといます。
タスク管理を仕組み化すると、この「頭の中での抱え込み」から解放されます。やることが目に見える形で整理されていると、それだけで安心感が生まれますし、心に余裕ができます。
私も以前は、夜になってから「あ、明日までの資料コピー忘れてた!」と慌てることが少なくありませんでしたが、タスクを可視化するようになってからは、そうした焦りはほとんどなくなりました。
時間の見通しが立ち、定時退勤に近づける
「今日はどこまで仕事が進むのか」が読めるようになるのも、タスク管理の大きなメリットです。
やることをリストアップし、所要時間をざっくりとでも見積もることで、「今日は18時までに終わりそうだな」と見通しを立てられます。そのおかげで、無理に残業することなく、退勤時間をコントロールしやすくなります。
私の場合、印刷作業を朝にまわすようにしただけで、放課後のバタつきが減り、結果として早く帰れる日が増えました。タスクを「時間」とセットで捉えることが、効率化の鍵だと実感しています。
教育の質が上がり、生徒との時間を確保できる
タスク管理の究極の目的は、単に「早く帰る」ことではありません。本当に大切なのは、授業準備や生徒とのコミュニケーションに十分な時間を割けるようにすることです。
タスクを整理して効率的にこなせるようになると、空いた時間を子どもたちとの関わりにあてられます。授業前のちょっとした準備、放課後の生徒との会話、これらは数字では測れない教育の質を高める大切な要素です。
仕事に追われる日々の中でも、「生徒と向き合う時間を確保できる」ことこそ、タスク管理の最大の効果だと思います。
まとめ|今日からできる小さな一歩
教員の仕事は多岐にわたり、どうしても多忙になりがちです。しかし、タスクを洗い出し、優先順位をつけ、アナログやデジタルのツールをうまく使い分けることで、日々の業務は確実に軽くなります。
私自身も、付箋や手帳、デジタルアプリを組み合わせ、さらに「放課後5分ルール」や「3色ペン方式」といった工夫を加えることで、残業時間を減らし、プライベートを大切にできるようになりました。
タスク管理は働き方改革の第一歩です。小さな工夫から始めてみることで、先生方の毎日に余裕と笑顔が生まれることを願っています。
先生になりたてのあなたへ|髪型の正解とNGをリアル経験から解説
教員こそファシリテーターへ|授業と業務を改善するファシリテーションの考え方
学校に行くのが辛い教員へ|ストレスマネジメントと“心の守り方”
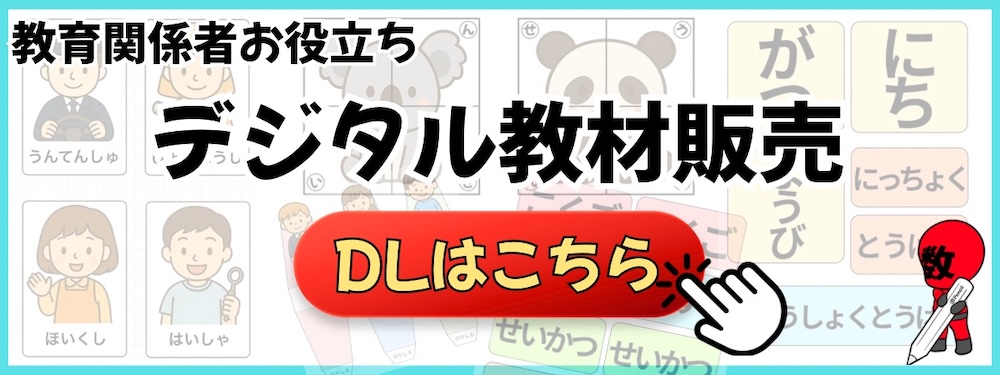
投稿者プロフィール

-
現役で数学を教えている中学校の先生です。中学の数学のプリントやICT関連の情報、ブログでは道徳や学級レクのネタも発信しています。
このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。
最新の投稿
 ブログ2026年2月25日学校で盛り上がる早口言葉15選|小・中・高校で使えるオリジナル集
ブログ2026年2月25日学校で盛り上がる早口言葉15選|小・中・高校で使えるオリジナル集 ブログ2026年2月23日【中学生・高校生向けレク10選】現役教員が実践して盛り上がった活動まとめ
ブログ2026年2月23日【中学生・高校生向けレク10選】現役教員が実践して盛り上がった活動まとめ ブログ2026年2月15日記号の名前いくつ知ってる?小中学生向け記号クイズ45問
ブログ2026年2月15日記号の名前いくつ知ってる?小中学生向け記号クイズ45問 ブログ2026年2月2日Keynoteの便利機能8選|知らないと損する使い方まとめ
ブログ2026年2月2日Keynoteの便利機能8選|知らないと損する使い方まとめ