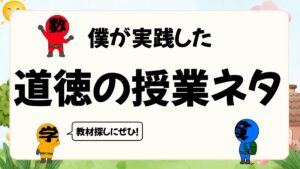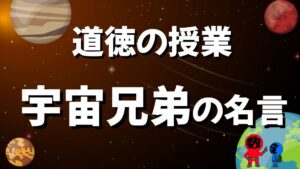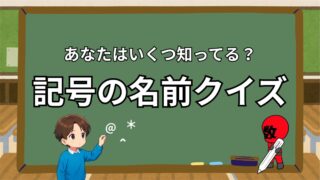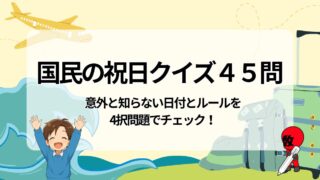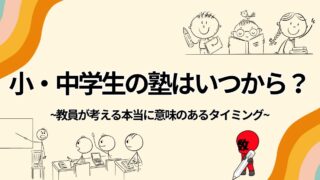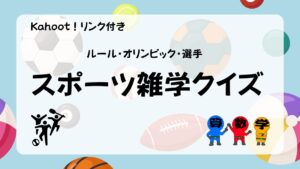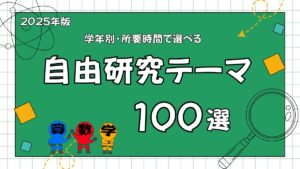「いただきます」という言葉の意味を、子どもたちはどれほど理解しているのでしょうか。
毎日の食事の中で、命の尊さや感謝の気持ちについて考える機会は、実はそれほど多くありません。
私は道徳の授業で、マンガ『銀の匙 Silver Spoon』の“豚丼”のエピソードを取り上げました。アニメという親しみやすい題材を活用することで、子どもたちは自然と物語に引き込まれ、「命をいただいて生きている」という重みを自分ごととして感じ取っていました。
この記事では、授業のねらいや展開、実際に子どもたちから出た言葉、そして教師としてこの題材を選んだ理由についてご紹介します。命や食について、子どもたちと一緒に立ち止まって考えるためのヒントになれば幸いです。

とてもおもしろい題材ですよ!
道徳のネタ紹介、僕が実践した授業40選!教材探しにぜひ
道徳の授業で使おう!漫画「宇宙兄弟」の名言
今回の授業で扱った『銀の匙 Silver Spoon』は、荒川弘さんによる人気マンガで、アニメ化もされた作品です。荒川さんは『鋼の錬金術師』の作者としても知られていますが、この作品では一転して、北海道の農業高校を舞台にしたリアルな青春物語が描かれています。
主人公の八軒勇吾は、進学校での挫折を経て、エゾノー(架空の農業高校)に進学します。農業に縁のなかった彼が、家畜の世話や酪農の現実と向き合いながら、「命を育てること」や「食べることの意味」に葛藤し、少しずつ自分自身を見つめ直していきます。
中でも、彼が育てることになった子豚「豚丼」とのエピソードは、作品の中でも特に印象的です。名前をつけて世話をし、愛着を抱く一方で、出荷され食肉になる現実を受け入れるというストーリーは、子どもたちが命と食の関係について深く考えるきっかけになります。
この授業のねらい
この授業で最も大切にしたかったのは、「命をいただいて私たちは生きている」という当たり前の事実を、知識としてではなく、“心で感じてもらう”ことでした。
日々の生活の中で、子どもたちは当たり前のように食事をし、「いただきます」と口にします。しかし、その食べ物がどこから来ているのか、どんな命だったのか、誰が手をかけてくれたのか……そうした背景に目を向ける機会は、そう多くありません。
『銀の匙』の豚丼のエピソードは、命を預かり、育て、最終的に“食べる”という選択をする主人公の葛藤を描いています。だからこそ、子どもたちは登場人物と自分を重ねながら、命の重さや複雑な感情を「自分ごと」として受け止めやすくなります。
私はこの授業を、正解を求める学びではなく、「考え続ける力」や「感じる力」を育てる時間として位置づけました。命に向き合うことに、簡単な答えはありません。けれど、自分の中に生まれた問いや違和感を大切にすることが、道徳の授業の本質であり、今の子どもたちにこそ必要な力だと信じています。
授業の構成
この授業は、子どもたちが命と食について「自分のこと」として考えられるよう、導入・展開・まとめの3つのステップで構成しました。
● 導入
まず初めに、マンガ『銀の匙 Silver Spoon』の舞台である北海道の農業高校や、主人公・八軒勇吾の人物像について紹介しました。進学校で挫折を経験した八軒くんが農業高校に進み、命と向き合う日々を送るという背景を説明することで、物語に入りやすくなるよう配慮しました。
続いて、彼が育てることになった子豚「豚丼」との出会いについて簡単に触れ、子どもたちの関心を引き出しました。
● 展開
物語のクライマックスである「出荷直前の別れのシーン」をアニメで視聴しました(約4分)。アニメの力によって、八軒くんの表情や感情がよりリアルに伝わり、子どもたちも自然と作品の世界に引き込まれていきました。
🟦 授業で使用したアニメ映像はこちら(約4分)
※動画では、豚丼との別れの場面を視聴しました。
アニメ視聴後は、豚丼との別れにまつわる八軒くんの行動や心情を読み取り、物語の意味を深く考える時間を取りました。以下のような発問を通して、思考を広げていきます。
- もし自分が豚丼の世話をしていたら、どんな気持ちになる?
- 八軒くんはなぜ泣いたのだろう?
- 豚丼の肉を、自分でお金を払って買って食べるという決断には、どんな意味がある?
- 「いただきます」という言葉には、どんな気持ちを込めている?
子どもたちは「自分だったらどうするか」という視点を持ちながら、命をいただくことの意味に向き合っていました。
● まとめ
授業の最後には、感じたこと・考えたことを一人ひとりが言葉にし、ノートやふりかえりシートに記述しました。その後、数名の児童が自分の考えを発表し、全体で共有しました。
私はこの時間の最後に、「この問いには正解はない。でも、自分の中に生まれた疑問や葛藤を、考え続けることが大切なんだよ」と伝えました。
子どもたちの中に芽生えた気づきや迷いが、これからの食との向き合い方や命に対する姿勢につながっていくことを願っています。
授業での配慮と工夫
「命をいただく」というテーマは、深く感動的な学びにつながる一方で、扱い方によっては一部の子どもにとって重すぎたり、不快な気持ちを与えたりする可能性もあります。そのため、授業を設計するうえで、いくつかの点に配慮をしました。
まず、肉を食べないご家庭や宗教的な背景を持つ子どもたちへの配慮です。食文化や価値観は人それぞれであり、今回の授業の目的は「食べることを正当化する」ことではなく、「命と向き合う視点を持つ」ことにあります。そのため、特定の価値観を押しつけることのないよう、考え方の違いがあることも冒頭で伝えました。
また、アニメの視聴や場面の紹介においては、過度に衝撃的な描写や直接的な表現を避けるようにしました。豚丼の出荷や処理については、あえて詳細には触れず、八軒くんの心の動きや葛藤に焦点を当て、「命に感謝する」という観点に意識を向けました。
さらに、子どもたちにとって難しいのは、「これが正解」と言えない問いに向き合うことです。だからこそ、教師自身が迷いながら問いに向き合う姿を見せることが大切だと感じています。私は、子どもたちの意見に一つひとつ丁寧に耳を傾けながら、「正解がない問いを考える」姿勢を自ら体現することを心がけました。
子どもたちが安心して自分の考えを出し合える環境を整えること。これが、命と食という重いテーマに向き合ううえで、最も重要な土台になると感じています。
まとめ|私がこの授業で伝えたかったこと
この授業を通して、私が子どもたちに一番伝えたかったのは、「命をいただいて私たちは生きている」という、当たり前だけれどとても大切な事実です。スーパーに並んだ食材の裏側には、誰かの手間や努力、そして命があります。そのことに気づくことで、子どもたちの「いただきます」という言葉が、少しでも変わってくれたらと願っています。
食べることは、生きること。毎日の食事が「ただの習慣」ではなく、「命をつなぐ営み」であることに気づいてほしい。そして、その気づきが、感謝の言葉だけで終わらず、食べ物を大切にする行動や、人への思いやりにつながっていってほしいと考えています。
正解のない問いに迷いながらも向き合う姿勢を、子どもたちはしっかりと見せてくれました。だからこそ、教師である私自身も、問い続ける姿勢を忘れずに、共に学び続けていきたいと思います。
道徳のネタ紹介、僕が実践した授業40選!教材探しにぜひ
道徳の授業で使おう!漫画「宇宙兄弟」の名言
投稿者プロフィール

-
現役で数学を教えている中学校の先生です。中学の数学のプリントやICT関連の情報、ブログでは道徳や学級レクのネタも発信しています。
このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。
最新の投稿
 ブログ2026年2月15日記号の名前いくつ知ってる?小中学生向け記号クイズ45問
ブログ2026年2月15日記号の名前いくつ知ってる?小中学生向け記号クイズ45問 ブログ2026年2月2日Keynoteの便利機能8選|知らないと損する使い方まとめ
ブログ2026年2月2日Keynoteの便利機能8選|知らないと損する使い方まとめ ブログ2026年1月30日【国民の祝日クイズ45問】意外と知らない日付とルールを4択問題でチェック!
ブログ2026年1月30日【国民の祝日クイズ45問】意外と知らない日付とルールを4択問題でチェック! ブログ2026年1月25日小・中学生の塾はいつから?教員が考える本当に意味のあるタイミング
ブログ2026年1月25日小・中学生の塾はいつから?教員が考える本当に意味のあるタイミング